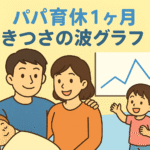休みに入って2ヶ月。がむしゃらに動いて、なんとか最初の1ヶ月を乗り切った。僕はヨガ、妻はエステ――それぞれの一人時間もうまく入れられていたはずが、上の子の発熱と自分の不調で3週間、運動に行けない日が続いた。土曜の朝は起きるのもつらいのに、「朝食は自分の役割だから」と気合で台所に立つ。そんなとき、妻の一言――「パパ、頑張りすぎてるかも」。そこでやっと気づいた。我慢しないで言葉にすること、そして交代で休むことが、家族の土台になるということに。
2ヶ月目で気づいた「頑張りすぎ」
育休開始から2ヶ月。最初の1ヶ月は、がむしゃらに動いて乗り切りました。1ヶ月の終わり頃、僕はヨガ、妻はエステでそれぞれ一人時間を入れてうまく発散できていた——はずでした。
↓最初の1ヶ月間の子育ての辛かった時期をグラフにしたので、こちらの記事もぜひご覧ください
その直後、上の子の発熱や、自分も風邪気味でヨガ・ジムに3週間行けない状況に。土曜の朝は起きるのもつらい。それでも「朝食は自分の役割だ」と頑張り、その日はその後もなんとか3食を作りました。
妻の従姉妹が遊びにきた時に、育休はどう?と聞かれ、妻は、「パパ頑張りすぎてるかも」と話していました。
夜に妻が「ご飯作るの辛い時とかないの?」と声をかけてくれました。素直に「先週の土曜がきつかったけれど、ママが夜起きて対応してくれていたからお願いもできなかった」と打ち明けると、「無理な時は言ってくれていいんだよ、とりあえず明日・明後日はヨガ(ジム)行ってリフレッシュしておいで」と背中を押してくれて、2日連続90分のヨガ+瞑想で一気に回復。翌日から2日間は妻がエステ→映画で一人時間。
我慢せずに言葉にする。交代で休む。 これが我が家の新しいルールになりました。
妻は「退院直後〜最初の1ヶ月」が一番きつかったと振り返っています。特に赤ちゃん返りが強かった上の子の対応が重なった時期が疲労のピークだったそう。ママの不調は産後すぐに出やすく(“マタニティブルーズ”は多くが産後数日〜2週間で自然軽快)、一方、パパの不調は3〜6ヶ月に高まりやすいという研究も。お互いの“波”がズレる前提で、早めの調整が大事でした。
僕たちが共有した「頑張りすぎサイン」5つ
- 朝、ベッドから出るのにいつもより2段階つらい
- 口では「大丈夫」と言いながらもイライラしたり無口になっている
- 腰の痛みなどの身体的疲労が強く出てきた
- 一人時間や睡眠時間が1週間で極端に少ない
- 家事負担が一方に偏ってしまった
本当は自己申告できるのが理想。でもお互いについ頑張ってしまう。
相手の様子が上のサインに当てはまるなら、相手から積極的に休みの確保を提案する、を我が家のルールにしました。
一人時間の作り方
来週分を先にカレンダーへ“予約”

色々なやり方があるとは思いますが、僕たちは来週の予定をお互いに早めに入れるようにしました。
これで、頑張る日、リフレッシュする日をお互いに先に確保し、見える化しました。
- 例)来週は火曜ママ:エステ/木曜パパ:ヨガ/土曜:パパと娘でプール/日曜:娘とママで映画など、カレンダーを共有し、お互いのリフレッシュ日をや予定を尊重。
体調や家庭の事情で変更はありつつも、「後回しにしない」ことで消耗を防げました。
役割は“軽く回す設計”にアップデート
- 節約<快適優先でOK:光熱費は多少かかっても、昼にもお風呂をためてリフレッシュ/洗濯は早めに回すなど
- 頑張りすぎない献立:副菜は1品少なくても合格。お互いにしんどい日は外食・惣菜・デリも積極的に採用
制度をフル活用:自治体×会社のダブル活用
- 自治体の「産後ケア事業」多くの市町村で、出産後1年以内の母子に対して助産師等による心身のケアや育児サポートが用意されています(利用条件・自己負担は自治体ごと)。まずは自治体サイトや保健センターに相談を。
- 家事・育児の外部化各地の産前・産後サポート/支援ヘルパーなど、家事・見守りを頼れる仕組みもあります(市区町村や社会福祉協議会等の事業として実施)。
- 会社の福利厚生(ベビーシッター割引)など、勤務先が導入していれば、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の**割引券などが(電子チケット)**が使える場合も。**1日1人あたり最大4,400円(2,200円×2枚)**割引、月24枚などの上限設定あり(詳細は全国保育サービス協会の案内や勤務先窓口を確認)。
“夫婦だけで抱え込まない”。祖父母・兄弟姉妹も会いたい&力になりたいはず。頼れる人には早めに役割をお願いすると喜ばれることも。
相談先(しんどいと感じたら)
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556(最寄りの公的窓口へ接続)
- よりそいホットライン:0120-279-338(24時間・多言語あり)
※本記事は医療アドバイスではありません。抑うつ・不安が続く/生活に支障が出る場合は、医療機関・公的窓口へ早めにご相談ください。
終わりに:我慢しない、言葉にする、交代で休む
「できてるつもり」でも、言葉にして初めて伝わる。
来週のリフレッシュを予定化し、役割は軽く回す設計に。制度も人もフル活用して、また2人で育児を頑張っていけたら。
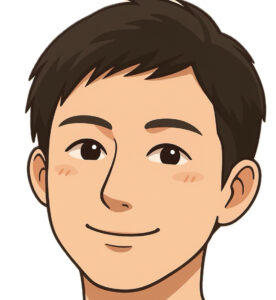
無理しなくていいんだよと言ってくれる妻に感謝。
私たちの最初の1ヶ月間の育休中のスケジュールはこんな感じでした。
出典URL(一次情報)
- 父親の産前・産後うつ(メタ解析:JAMA, 2010):3〜6ヶ月で相対的に高いhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20483973/
- 日本人男性の周産期うつ(メタ解析, 2020):3〜6ヶ月にピークhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33292315/ / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7677771/
- マタニティブルーズ(日本産婦人科医会):産後数日〜2週間程度で自然軽快https://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200226/
- 産後うつ(日本産婦人科医会):3ヶ月以内に発症が多いhttps://www.jaog.or.jp/qa/confinement/jyosei200311/
- 自治体の産後ケア事業(こども家庭庁・資料):出産後1年以内を対象に心身ケア等を実施https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0238af12-b583-4c09-9a67-0f2f7cb19c1c/028b6e96/20241120_councils_shingikai_seiiku_iryou_0238af12_04.pdf
- ベビーシッター割引券(全国保育サービス協会ガイド):1日1人あたり最大4,400円(2,200円×2枚)割引、月24枚などhttps://www.acsa.jp/images/babysitter/babysitter-ticket-guide.pdf
- (参考)制度窓口・概要(こども家庭庁)https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/ryouritsu
※本記事は個人の体験と一般情報の共有であり、診断・治療・専門的助言の代替ではありません。心身の不調が続く・強まる場合は、医療機関や公的窓口に必ずご相談ください。