育休に入って1ヶ月。
毎日赤ちゃんと過ごす幸せな時間の裏で、いつもどこかにある「お金」の不安。
育児休業給付金が振り込まれることが遅いことは理解していたし、『貯金があるから大丈夫』と思っていました。
でも、実際に生活してみると勘違いや、想像以上の出費が。
この記事では、僕が実際に感じた金銭面のリアルや、「もっとこうしておけばよかった」と思った反省点をまとめました。
育休1ヶ月、早くも収入ゼロ状態に…
私は6月の出産と同時に育休に入りました。もらえる手当と支出を何度もシミュレーションし、絶対に大丈夫との自信がありました。
しかし今考えれば当たり前なのですが、普段残業代が翌月に支給されていることから、給料は後払いという勘違いをしていました。
7月末の給料日が最後満額支給だと思っていたのです。
ですが、入金されていたのはもちろん6月の残業代だけ。
早くも数十万円単位で計算が狂いました。
同じようなミスをしないためにも、改めて手当の額とタイミング、出費に関してまとめます。
入金額と出費の経過
計算を簡単にするため、給料を30万円、1ヶ月の出費額(生活費)も30万円とします。
| 月 | 入ってくる内容 | 入金額 | 出費の内容 | 出費額 |
|---|---|---|---|---|
| 6月(出産、育休開始) | 給料(最後の満額支給) | 30万円 | 生活費 出産費用(一時金50万円引く) | 30万円 40万円 |
| 7月 | 残業代 付加給付金(31日支給) | 4万円 9万円 | 生活費(生活コストは下がっても、赤ちゃん用品でトントン) | 30万円 |
| 8月 | 児童手当(6、7月分の支給) 生まれた翌月から支給開始のため、赤ちゃんは1ヶ月分のみ | 上の子1万円×2ヶ月=2万円 下の子1.5万円×1ヶ月=1.5万円 | 生活費 | 30万円 |
| ここまでの合計 | 46.5万円 | 130万円 | ||
| ここまでの赤字額(必要貯蓄額) | 83.5万円 | |||
| 9月 or 10月 | 最初の育児休業給付金 |
出産付加給付の9万円は加入の健康保険により給付の有無を含め、内容が異なります。育児休業給付金と同タイミングになることもあるようです。
ご覧のように、最初の育児休業給付金の支給は育休開始後3ヶ月〜4ヶ月程度後と言われています。
出産費用や、生活費の額にもよりますが、取得予定の月数×手取り月収+出産費用は最低限貯蓄が必要になることが分かります。
育休1ヶ月目は実質10割とも言われますが、支給タイミングが遅いため必要な貯蓄額は変わりません。
出産費用も予想以上に高額となることがあります。【体験談】無痛分娩の費用は90万円!出産費用の内訳と補助制度を徹底解説
育休中の税金、社会保険料
- 社会保険料・・・育休中の社会保険料は免除になります(月末を含む場合など取得期間によって異なります)私の場合は、6月末から1年の育休取得だったため、6月の賞与の社会保険料も免除対象となり、明細の控除蘭への記載もありませんでした。
- 住民税・・・住民税は、前年の1月から12月までの収入に対する税金を、翌6月から5月で支払う税金です。そのため、育休取得年に支払う住民税は安くはなりません。収入が減少した分は、育休取得翌年の住民税額に影響します。また、1年のように長期間取得する場合は、特別徴収(毎月の給料から天引き)から普通徴収(自治体から送られてくる通知書を元に自分で基本は4分割で支払い)に切り替わることもあります
- 所得税・・・給与所得に対する税金であり、1ヶ月ごとに給与天引きされ年末調整で調整されます。給料がない月は支払いがなく、もし足りなかった場合には年末に徴収されるということが多いと思われます。
事前にもっと備えておけばよかったこと
- 収入と支出のタイミングを表にまとめて、詳細なシミュレーションを行う
- 出産費用は一番高いと思われる額で念の為計算しておく
- 給料や会社からの祝金、付加給付金などのタイミングを総務課や事務担当者に確認しておく
- 家計(支出)の見直しを行う
- ボーナスのタイミングが近いからとあてにし過ぎず、事前に貯蓄しておく
それでも安心できた理由
- 年収額以上の貯蓄額
- 10年間の投資経験と、株の配当(年間10万円)
- 夫婦ともに楽天株主優待での無料SIMを使用することによるスマホ通信料0円化
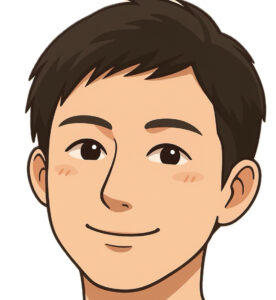
いくら夫婦で家事を分担して、精神的に余裕があっても金銭的不安が大きければ育休はしんどいはず
貯蓄と、多くはありませんが株の配当で少しでも家計がプラスとなるものがあることで安心できました
他にしたこと
- 使えるポイントの集計と支払いへの充当
- クレジットカードの解約と新規発行
- サブスクリプションの見直しと解約
- 家の更新料など、支出の値下げ交渉
- 住民税の普通徴収への変更タイミングの確認
普段は貯めっぱなしにしていることが多い各種ポイントを洗い出し、支払いに充当しました。
育休中の税金や社会保険料に関して理解を深めるのも重要です。大体の支払い金額とタイミングを確認しておきましょう。
まとめ:育休開始1ヶ月、事前準備と情報収集の重要性
育休は貴重な家族との時間であり、人生の一大イベントでもありますが、同時に「収入減」と「支出増」が重なる経済的に試練の期間でもあります。
今回の経験を通して、次のようなポイントが非常に重要だと感じました。
- 育休手当が入るまでのタイムラグは3〜4ヶ月あることを理解し、最低でも3ヶ月分の生活費+出産費用を用意しておく
- 「健康保険料の免除」や「住民税の納付タイミング」など、制度を事前に確認して対応策を立てておく
- 家計簿や支出シミュレーションを細かく行い、想定外に備えることが安心につながる
- 収入ゼロでも「なぜ大丈夫なのか」を冷静に説明できるようにしておくと、家族間での不安も軽減できる
育休は育児だけでなく、家計やライフスタイルを見直す絶好の機会でもありました。
これから育休を検討している方にとって、この体験が少しでも参考になれば幸いです。
※本記事はFP2級の知識に基づいて執筆していますが、最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。