結論:育休に入ると住民税は「会社天引き→自分で納付」へ
育休に入ると給与の支給が減ったりなくなったりするため、住民税は「特別徴収(会社天引き)」から「普通徴収(自分で納付)」へ切り替わることがあります。
僕のケースでは、8月上旬(8/5)に納税通知書が届き、6月に天引きされた額以外の残りを3回で納めることになりました。第2期の支払い額は6月に天引きされた住民税の約3.6倍で、タイミング的に出産手当金・育児休業給付金はまだ未入金。完全に貯金からの持ち出しで、預金確保の重要さを痛感しました。
※ 納期限や回数は自治体により異なるため、正確な日付は必ず通知書でご確認ください。本記事では匿名性のため**「月上旬/月末ごろ」などの表現でぼかしています**。
我が家のケース(時系列)
6月末から育休スタート/6月は給与、満額支給
- 育休の開始時期は6月末。
- 6月の給与は満額支給。このタイミングでは住民税は**特別徴収(会社天引き)**でした。
7月は残業代のみ、8/5に納税通知書が到着
- 7月は残業代のみの支給のため、住民税の天引きはなし。
- 8/5に住民税の納税通知書が到着し、ここからは**普通徴収(自分で納付)**へ。
支払いは3分割・第2期は6月天引きの約3.6倍
- 年額から6月に天引き済みの1か月分を差し引いた残額を、3回に分けて納付。
- そのため第2期の納付額 ≒ 6月天引き額の約3.6倍になりました。
PayPayの請求書払い(クレカ決済)で引落は9月末
- 納付書のバーコードをPayPayで読み取り、PayPayクレジットカード払いに設定。
- 引落は月末(僕の場合は9/27予定)になり、一時的に手元の現金は減らないものの、給付金の入金時期が読みにくいので貯金は確保しておきました。
※ キャッシュレス納付の可否・方法・手数料やポイント付与可否は自治体・決済手段により異なります。必ず通知書・公式案内をご確認ください。
妻は5月から産前産後休業→6月初旬に通知、最初から普通徴収
- 妻は5月から産前産後休業に入っており、6月の給与はなし。
- そのため最初から普通徴収となり、6月初旬に納税通知書が到着。
- 夫婦とも同時期に住民税の納付が重なるため、預金の確保を前もっておく必要がありました。
仕組み解説:なぜ金額が一気に大きく感じるのか
- 特別徴収(会社天引き):年額を概ね12分割して毎月の給与から天引き(通常6月〜翌年5月)。
- 普通徴収(自分で納付):年額または残額を数回(多くは3〜4回)で納付。
- 途中で特別→普通に切り替わると、「1/12」ペースから「1/3」ペースへ変わるため、1回あたりの負担が大きく感じやすいのがポイントです。
納付スケジュールと金額感(ぼかし版)
正確な納期限は自治体の通知書に従ってください。ここでは僕の通知書を元に、匿名性を保つ表現に置き換えています。
| 期別 | 納期限(例) | 金額 |
|---|---|---|
| 第1期 | 6月末分(経過済みのため0円) | 0円(6月に特別徴収済み) |
| 第2期 | 9月上旬ごろ | 6月天引き額の約3.6倍 |
| 第3期 | 10月末ごろ | 第2期と同額 |
| 第4期 | 翌年2月上旬ごろ | 第2期と同額 |
- 第2〜第4期の3回で残額を等分。それぞれ年額の1/3ずつのイメージです。
- 僕は第2期の支払期限が9月上旬で、給付金(出産手当金/育児休業給付金)はまだ未入金。よって貯金からの支払いとなりました。
キャッシュフロー対策:給付金のタイムラグに備える
- 普段の毎月の天引き額 × 約3.6倍 × 夫婦分を一時の目安に、生活費とは別枠で確保しておく。
- 入金予定が読みにくい給付金は“入金後に補填”する前提で、先に現金(または引落枠)を確保。
- 支払い方法は口座振替/コンビニ/スマホ決済(バーコード)/クレカ等、自治体が許可する方法から選択。
- 納期限は必ず守る(延滞金リスク)。どうしても厳しいときは早めに役所へ相談。
- 家計の一時的な見直し(サブスク整理・特別支出の先送り)でキャッシュを厚めに。
ふるさと納税の影響と注意点(育休の年は“上限”が下がる)
前年に行ったふるさと納税の控除が、今年の住民税(今回の通知)に反映されていて、わが家も減額されて助かりました。
一方で、育児休業給付金は非課税のため、育休に入った当年の課税所得は下がりやすく、ふるさと納税の“上限額”も大きく下がります。上限を超えて寄付すると超えた分は原則控除されず自己負担になるので要注意。
注意
- 今年は給与が減る or 0の月がある → 所得割額も縮小 → 上限も縮小(高年収の人ほど減少幅は大きい)。
- 迷ったら年末ギリギリに最新の収入見込みで再試算し、余裕資金の範囲で寄付が安全。
いますぐできるチェック
- 今年の見込み給与収入・社会保険料・各種控除をざっくり書き出す
- ポータルの上限シミュレーターで今年の見込み年収を入れて再計算
- 配偶者の収入・控除の変化(育休中で収入減など)も反映
- ワンストップ特例を使うなら5自治体まで・寄付の翌年の住民税で控除される点を再確認
メモ:普通徴収(自分で納付)に変わっても、前年寄付分の控除は翌年の住民税に反映されます。途中で給与天引き→自分納付に切り替わっても、控除自体は失われません。
よくある質問(FAQ)
Q. 納税通知書はいつ届く?
A. 最初から普通徴収の場合は、僕の自治体では6月上旬に到着。ただし自治体によって時期は前後します。
Q. 会社天引きから普通徴収に切り替わる条件は?
A. 給与支給がなくなる/減るなどで特別徴収の継続が難しい場合に、普通徴収へ切替になることがあります(実際の手続き・判断は会社と自治体の運用によります)。
Q. 1回の納付額が大きい。分割はできる?
A. 多くの自治体で期別ごとに分かれた納付書が届きます(3〜4回)。それ以上の分割可否は自治体に要確認。
Q. スマホ決済やクレジットカードで払える?ポイントは?
A. 対応可否・手数料・ポイント付与の有無は自治体・決済手段によって異なるため、通知書の案内や公式サイトを必ずチェックしてください。僕はPayPayのバーコード読み取り→PayPayクレジットカード払いにしました。
Q. 育休の年に、昨年と同じ金額をふるさと納税しても大丈夫?
A. 所得が下がるなら上限も下がる可能性が高いです。去年と同額は危険。年末に収入見込みを更新して上限再計算を。
Q. 上限を超えたらどうなる?
A. 超過分は控除されず自己負担(翌年以降へ繰越は不可)。慎重に。
Q. 夫婦で同時育休。上限は合算できる?
A. 各人それぞれで判定。それぞれの課税所得・控除で個別に上限が決まります。
まとめとチェックリスト
- ✅ 育休で特別徴収→普通徴収に切替→自分で納付へ
- ✅ 途中で普通徴収となった僕の通知は8月上旬に到着
- ✅ 第2〜第4期の3回払い。第2期は6月天引きの約3.6倍でインパクト大
- ✅ 給付金はこの時点で未入金→貯金取り崩しを想定
- ✅ スマホ決済・クレカ決済は自治体の対応を要確認
- ✅ 夫婦同時期に重なると負担感が増す→事前の資金確保が安心
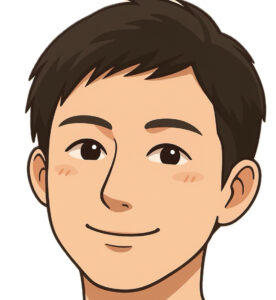
この記事が、これから育休に入る方や、住民税の通知が届いたばかりの方の参考になれば幸いです。納期限・支払方法は自治体により異なるため、最終的には通知書の記載を優先してください。
住民税以外の支出についてはこちらの記事をご覧ください!
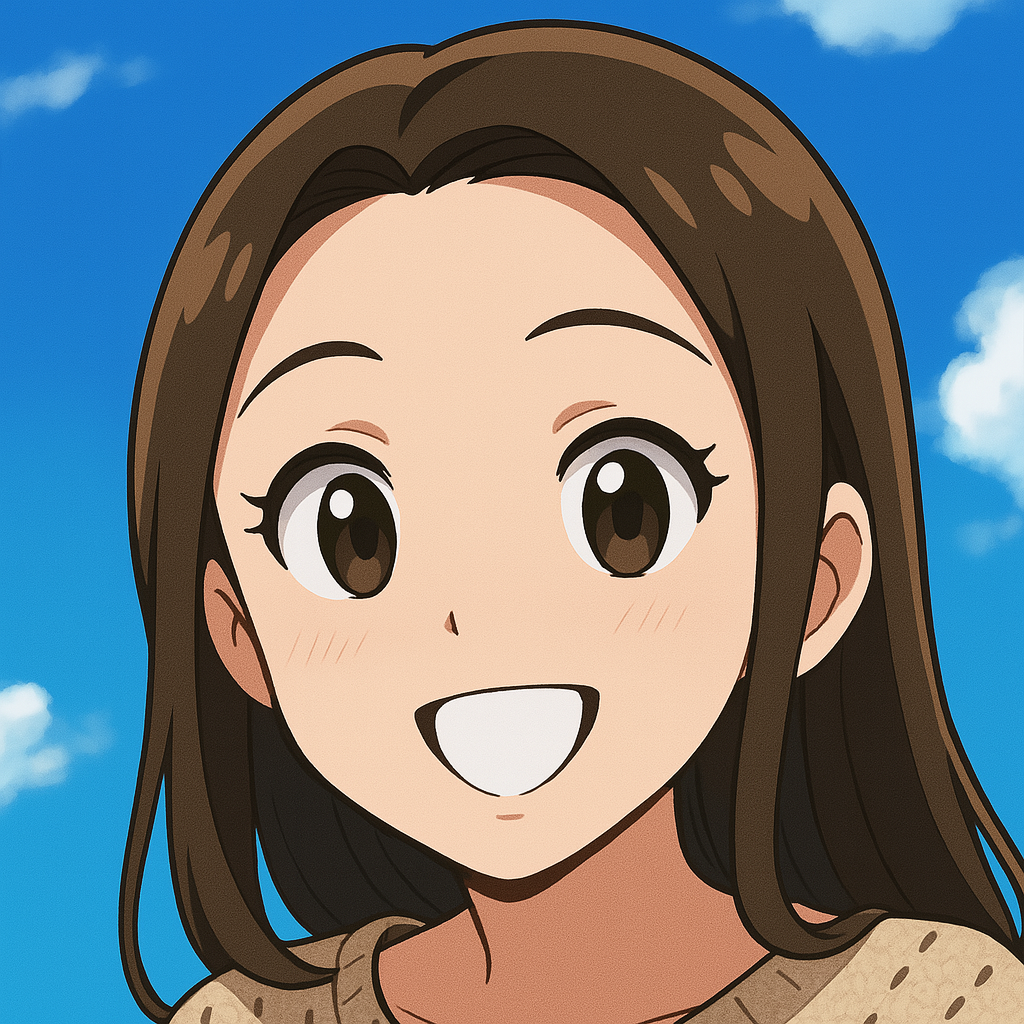
※本記事はFP2級の知識に基づいて執筆していますが、最新かつ正確な情報は必ず厚生労働省や自治体などの一次情報をご確認ください。
