本記事は2025年8月時点の厚生労働省資料をもとに作成・検算しています。主要出典は文末を参照。
この記事でわかること
- 育休と**産後パパ育休(出生時育児休業)**の違い(分割取得・就業可否など)
- パパに関わる給付金の種類(育児休業給付金/出生後休業支援給付金/出産育児一時金)
- 「実質手取り10割」の根拠と上限(キャップ)
- 月収20万〜45万+上限の受取目安・計算方法
- いつ頃入金されるかの目安
- 上の子の保育園はどうなる?
- 僕が「産後パパ育休は使わず、育休のみ」を選んだ理由
育休と産後パパ育休の違い(まず全体像)
| 項目 | 育児休業(育休) | 産後パパ育休(出生時育児休業) |
|---|---|---|
| 取得可能時期 | 原則1歳まで(最長2歳まで延長あり) | 出生後8週間以内 |
| 分割取得 | 最大2回までOK | 最大2回/合計28日までOK |
| 就業の可否 | 原則不可(就業が多いと不支給) | 一部就業可(上限あり) |
| 主な給付 | 育児休業給付金(開始〜180日は67%/181日以降50%) | 出生時育児休業給付金(67%)+出生後休業支援給付金(+13%)=合計80%(最大28日) |
分割上限・期間・就業上限は厚労省リーフレットに明記されています。
パパが知っておくべき給付金
- 育児休業給付金休業開始から180日までは67%、181日以降は50%。非課税で、育休中は申出により健康保険・厚生年金の保険料免除あり。
- 出生後休業支援給付金(2025/4新設)出生時育児休業給付金または育児休業給付金の上乗せ13%。要件を満たすと、出生後8週間内の最大28日が合計80%(=手取り10割相当)になります。※賃金日額に上限あり。
- 出産育児一時金公的医療保険から1児あたり50万円(原則)。
「実質10割」の根拠と上限額(キャップ)
- 「実質10割」は、給付が非課税で、かつ育休中の社会保険料免除があるため、給付率80% ≒ 手取り100%相当とされることによります(対象は最大28日)。ただし休業開始時賃金日額には上限があり、超えると頭打ちになります。
- 2026年7月31日までの代表的な**支給上限(30日換算)**は次のとおり:
- 67% 上限:323,811円
- 50% 上限:241,650円
- 13%(上乗せ/28日最大):58,640円※賃金日額上限16,110円、下限3,014円/日。
上限に達する月収の目安は約483,300円(= 323,811 ÷ 0.67)。ここを超えると67%・50%・13%すべて上限で頭打ちになります。
計算方法(かんたん版)
- 賃金日額 = 育休開始前6か月の総賃金 ÷ 180
- **育児休業給付金(1か月目安)**= 賃金日額 × 支給日数(例:30日) × 67%(181日以降は50%)
- 出生後休業支援給付金= 賃金日額 × 対象日数(最大28日) × 13%
- いずれも上限・下限あり(上記参照)。
実務上は「月収×率」でほぼ同じ結果になります(本記事の表は30日月で概算)。
月収別の概算(30日月/円未満四捨五入)
「+13%」は最大28日を取得した場合の上乗せ分だけを示します(= 28日分×13% 相当)。
67%→181日以降は50%に切替。すべて上限の範囲内で計算しています。
| 月収(額面) | 初回〜180日(67%) | 181日以降(50%) | +13% 上乗せ(28日最大) |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 134,000円 | 100,000円 | 24,267円 |
| 250,000円 | 167,500円 | 125,000円 | 30,333円 |
| 300,000円 | 201,000円 | 150,000円 | 36,400円 |
| 350,000円 | 234,500円 | 175,000円 | 42,467円 |
| 400,000円 | 268,000円 | 200,000円 | 48,533円 |
| 450,000円 | 301,500円 | 225,000円 | 54,600円 |
| 上限相当(月収約483,300円) | 323,811円 | 241,650円 | 58,640円 |
注:就業(働いた)日数・時間、会社からの賃金支払がある場合は減額・不支給になり得ます。詳細な減額式はリーフレットを確認してください。
いつ頃入る?(支給タイミングの目安)
- 給付は支給単位期間=1か月ごとに認定されます(30日・31日・28日月で変動)。
- 出生時育児休業給付金の申請は、原則「28日に達した翌日」または「2回目の産後パパ育休終了翌日」から可能で、申請期限は開始日から2か月を経過する日の属する月末です。初回の振込は事務処理の都合で数か月後になることがあります。
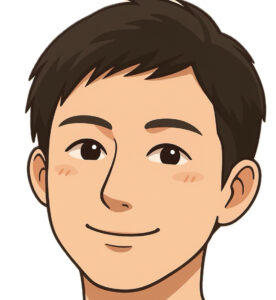
産後パパ育休(約1ヶ月の育休)を取得する場合でも、出費は多いのである程度の貯蓄が必要です。
上の子の保育園はどうなる?
- 基本的に継続通園は可能ですが、育休中は就労要件が変わるため、短時間認定や保育時間調整になることがあります。自治体・園の要綱を事前に確認しましょう。
僕が「育休だけ」を選んだ理由(体験ベース)
- 産後パパ育休(最大28日・2分割可)→その後に育休へつなぐ選択もできるが、仕事をする必要がなかった(完全引継ぎ済)。
- 会社への申請が1枚で済み、手続きがシンプルだった。
- 実質10割は育休のみの取得でも対象であり、産後パパ育休を取らないデメリットは実感せず、育休のみで十分と判断し、育休のみにした。(産後パパ育休は一部就業可だが、就業日数・時間の上限超過で不支給になる点は要注意。)
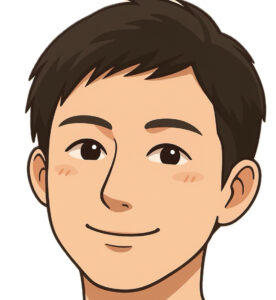
会社とのやりとりなどはこちらの記事をご覧ください
参考:用語と要件の押さえどころ
- 分割取得:育休・産後パパ育休とも最大2回まで。※どちらも取得するなら最大4回に分割して取得が可能となる。
- 実質10割:非課税+社保料免除+出生後休業支援給付金13%上乗せにより、対象28日は合計80%=手取り100%相当。ただし上限あり。
- 出産育児一時金:50万円/1児(原則)。
出典(主要ソース)
厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続(2025/8/1改訂版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
厚生労働省「『出生後休業支援給付金』を創設しました(手取り10割相当の考え方・上限16,110円)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
厚生労働省「育児休業等給付について(制度概要・育休/産後パパ育休の分割回数など)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
厚生労働省「雇用保険 事務手続の手引【第3編】(出生後休業支援給付金の計算・上限58,640円 等)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001531308.pdf
厚生労働省「出産育児一時金(原則50万円)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html
よくある質問(簡潔版)
Q. 育休は2回に分けられる?
A. はい。最大2回まで(産後パパ育休も2回・合計28日まで)。
Q. 「実質10割」はいつ?
A. 出生後8週間内の最大28日が対象。67%+13%=80%で、非課税+社保免除により手取り100%相当になります(上限あり)。
Q. 上限にまず当たるのはどのくらいの月収?
A. 目安約48.33万円。以降は頭打ちで、67%=323,811円/50%=241,650円/13%(28日)=58,640円が上限。
まとめ
- 育休は最長2歳まで延長可、分割2回。産後パパ育休は出産後8週内で最大28日・2回。
- 給付は67%→(181日以降)50%、出生後の**+13%(最大28日)で実質手取り10割相当**の期間あり(※上限あり)。
- 月収20〜45万+上限の目安表を使って、家計の見通しと申請スケジュールを先に決めましょう。
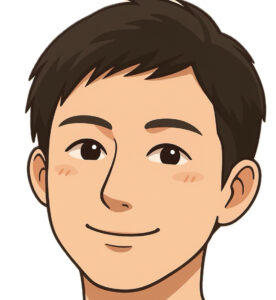
制度は難しく見えるけど、“いくら入るか”と“いつ入るか”がわかれば怖くない。この記事が準備の最初の一歩になればうれしいです!
※本記事はFP2級の知識に基づいて執筆していますが、最新かつ正確な情報は必ず厚生労働省や自治体などの一次情報をご確認ください。

